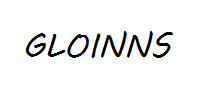Aki Machida
1989年にHPから教わったビジネスプランです。古いと思われるますか?でもシリコンバレーのOSとも言われるデザイン思考は、10 Step Business Plan のコア部分であるStep3からStep6が相応しています。
日本HPでTQCが盛んな頃、アメリカ本社でもQC的考え方が見直され、1989年にZipper2(Zipper2のブログ参照)のプロジェクトチームのマーケティング責任者として出向したときに、体得した手法がこの 10 Step Business Planです。私はプロダクト・マーケティングでしたので、その経験から説明します。リストは以下のとおりです。今でもChatGPTにビジネスプランの方法を聞くと自社の技術や優位性の棚卸しの後に、こういう順番でやれと出てきますので、基本的な戦略として常識化しているのでしょう。
1. Statement of Purpose
2. Five Year Plan
3. Market
4. Competitor
5. Necessary Product and Service
6. Development Plan
7. Financial Analysis
8. Potential Problem Analysis
9. Recommendation
10. Hoshin Plan
GoogleやChatGPTでビジネスプランを検索すれば、3Cだの4Pだの沢山模範解答が出てきます。しかしながら、実際のプランニングは公にされない情報や未知の情報を見つけ出すことにありますから、とてもAIや一人では出来ません。チームメンバーはR&D、マーケティング、製造、経理です。人数は多すぎてもいけませんし、期間も大学のワークショップのように1週間程度で出来るものでもありません。
チームの結成は事業部長から支援を受けるので、チーム意識を高めるためにチームロゴを作って、ロゴ付きのポロシャツなどを用意していました。
プランニングは普段の仕事をしながら、推敲を繰り返し、3回は練り直します。ざっと24-7くらいの集中で3ヶ月はかかるでしょう。AIでかなり作業短縮は出来るでしょう。ただし、現時点での現場で現実を検証しながらですので、時間はかかります。
AIの意見が入ってくると、時々いい加減なので、その確認も必要になるので、場合によっては余計に時間がかかるかもしれません。
最近は政治的なゲームチェンジが多いものの、近い将来やってくる状況というのはだいたい見当がつきますよね。自分たちが既にその市場に居るなら競合なども明白です。
ということで、はじめの一歩は#3の市場調査からです。
第一回目に素早いドライな調査でターゲットの市場をサイズと成長率を把握し、めぼしい分野を3つくらい選びます。
ChatGPTを市場調査に使うのはある程度良いと思います。ただし、フレームワークだけの紹介になりますし、最新の情報や実際何が起きているかという情報が欠けていたりしますから、他の方法を検討・駆使することになります。
ここで時間(人件費と機会損失)を無駄にしないためにIDEAPOKE、HackJapan、SPEEDAなどの調査機関を使うのは得策です。その間にメジャーカスタマーに訪問や聞き取りをして、困りごとを探せるからです。
ただ、この時聞く人を間違えると簡単に失敗します。不平不満は他責にされてますし、その人の評価軸で優先順位が決まりますから、ちゃんと「4人のバイヤー」(StrategicSellingを参照)
https://global-innovator-solutions-u9k9b.zensmb.com/strategic-selling
を探して調査します。既存顧客の場合は容易です。しかし、殆どの場合、新規顧客になりますから想像するだけでも大変です。
#3の活動の間に競合情報も入ってきますので、その都度、ドライな会社情報や公にされている戦略を調べます。
大抵の場合、競合は既にターゲット顧客とビジネスの関係がありますから、どれくらいの強さで繋がっているか調べます。このステップではリサーチスキルとコミュニケーションスキルが要ります。ここまで来るとSWOTチャートの右側が描けるようになり、#4が大方完成します。
#5は大論争の始まりです。何が求められているのか、QCDSだけでなく、性能を定義するために要求品質表(QFD)を纏めます。
開発の人は先回りしてProductDefinitionを持っている場合もあります。残念ながら、往々にしてこうしたProductOutな製品やサービスは顧客不在で社内のサポートが得られにくいので、組織としての成長シナリオが描けません。
StrategicSellingのBLOGにも書きましたように、「売れる」「買ってもらう」のは3つのモードのお客様だけです。それはグロースモード、トラブルモード、インフルエンサーです。お金がない、邪魔しないでほしい、現状で十分満足しているという方々には、テクニックを使って共感を持って頂かないと絶対に進捗しませんから、本当のニーズを引き出すのはとても難しいです。
例えば今話題の電気自動車です。距離が伸びないから買わないという、ガソリン車とガソリンスタンド網で満足している方による理由が一番大きいかと思います。しかしながら、高速を2時間運転したら、休んだほうがいいわけで、余裕を持って寒い冬でも250Kmくらい走れれば十分なのです。むしろサービスエリアに沢山の高速充電器があって、30分程度で80%まで充電できれば良いので、この場合300Kmの定格のバッテリーで殆どのユーザニーズはカバーできてしまいます。つまり本当のニーズは高出力の高速充電網があって、充電で並ばずに済むだけ十分なステーションがあれば良いということになるわけです。日本の高速道路のサービスエリアには非力なCHADEMOが数機あるだけで30分制限がありますから、EVが静かに締め出されている事が分かります。
ですからちゃんと#6の開発計画でコンセンサスを取りながら実現性を具体的にしてゆきます。場合によってはこの時点で青写真を見てもらいます。
#7で経理の人に入ってもらい、6M(人、物、金、方法、製造、測定)で性能ごと、スケーリング計画ごとにシナリオを3本くらい作って、いつからどれくらいの売上規模になって、いつBE(BreakEven)で、どのくらい儲かるかを纏めます。
単価下落も考慮して、利益率は年次で30%から15%くらいのカーブを狙います。
製品にはそれだけのBENEFITが提供できるよう、アドバンテージが十分ある特長(FEATURE)が求められます。このFABが明確であれば明確であるほど成功の可能性は高くなります。
よく、値下げをしないと売れないと言う営業さんがいますよね。Benefitの無い商品や、Benefitの理解・訴求してくれる営業さんでない場合、商品開発は目測を誤ったと言えます。値下げしないと売れないのでは、せっかく努力してくれた工場や開発に対する侮辱です。YHP時代はHP製品の定価販売を押し通していました。購買部長が怒って、値下げ交渉のために上司を連れて来いと言ってきても、上司は一銭も値下げに応じません。営業担当者の給料を下げるようなことは出来ません、と。半導体業界では、供給が逼迫すると、利益率の高いお客に優先度を上げてアロケーションしている会社があります。立派なロイヤルティプログラムです。私が担当する部品でも、需給が逼迫した場合は納入実績の多いお客様にアロケーション配分を多くし、値下げ要求をかわしました。
#8では予測の前提が崩れたらどうするか対応策まで用意します。ここまで来ると、チームのミッションが明確になりますから、#1が書けます。
#9で最初の上層部・幹部からのアドバイスを貰ってフォーカスするシナリオを決定します。
さらに、#10の管理項目を決めて方針表を用意、#2の5カ年計画表をサマライズすると、完成です。
#1から#10までプレゼンはメンバー全員によるリハーサルを3回はやります。事業会議でこのパフォーマンスを披露して、出来ればその場で最終的なサインオフをもらいます。
InvestigationPhaseの終了です。
ご想像通り、一発で承認されることはないので、ひどい場合はマーケットリサーチまで戻って、やり直しです。
これらの#3から#8は日本でもステージゲートのコンセプトが広まっていますからお馴染みがあるでしょう。
とにかく、これで初めて、最小規模の設備の導入の注文や新しい人員探しが公式にはじめられます。DevelopmentPhaseの始まりです。モックアップや試作が出来たら、先程のお客のところにすっ飛んでいって、NDA結んでフィードバックをもらいます。実物を見せると本当にたくさんの意見が得られます。気に入って頂いたお客様には先行販売契約を提案します。これが大成功の鍵です。次の試作を持って来いと、追い返すお客はどんなに大きな数量が期待できても優先順位を下げましょう。
それでも場合によってはケチョンケチョンに言われますので、酷い場合はProductDefinitionまで突き戻される可能性があります。PDCAの繰り返しですね。
試作が気に入られたら、会社同士の付き合いに発展させ、クロージングのとどめを入れて、開発オーダをもらいます。ここがManufacturingPhaseに移行できるかの肝です。
この試作オーダの要求を躊躇すると先方の責任感も薄れます。社内も日々入ってくる新しい情報でブレ始めます。注文書が来たら、まずは祝杯です。
お客様が優先供給を申し出てきたらしめたものです。イニシャルキャパシティーを買って頂けるなら、マーケットリリースを3ヶ月とか6ヶ月遅らせることも出来ますし、すでに社内人気が出ている場合には営業さんの調整など矢面に立たされます。
戦略的な注文を取れなかった営業さんは指をくわえるしかありません。ですがお客様が寝返らないように別の友好条件を用意するなどして赤い糸が切れないようにします。
マーケットリリースの時点で供給のアロケーションが必要なら、大成功と言って良いでしょう。ただ、気を緩めてはいけません。製造で歩留まりが悪く、バックログが解消できないようであれば、工場に行って一緒に問題解決しましょう。スペックダウンしても大丈夫なお客様には仕様変更したものを短期的に受け入れて頂く提案もあります。
お客様での受け入れ品質や製造品質が悪いと聞けば飛んで行って、どうなっているのか調べます。
実際、10000PPM不良のクレームのときには中国の工場ラインに入って、問題点を見つけ、取り扱い方を変更していただくとともに、データシートやアプリケーションノートを書き換えて、歯止めを打ちました。
ドキュメント管理も徹底しないと、古い資料のお陰で、不良が止まらない場合があります。日本の場合は納入仕様書管理がありますから、変更内容の通達が出来る点は素晴らしいと思います。
いかがでしょうか?お客様と供給側それぞれに、営業、特約店、マーケティング、開発、製造、品管、経理、業務、経営層などがあり、それらは少しづつ位相がずれてますから、それを理解しながら入念に計画を進めるのは本当にマーケティング冥利につきます。これで売上が上がって、利益が確保出来れば次の課題への自信となるのです。
(ページの冒頭のイメージはネブラスカ大学から拝借しました)
もっと聴きたい、という場合は予約を入れてください。
Calendlyで1時間予約を入れて下さい。30分無料で、続けたい場合は次の30分$100です
Zoomはそちらでセットアップしてください。録画もお勧めします。
自己紹介のEmailは事前にお願いします。
最初は履歴書だけでもLinkedInだけでも結構です。