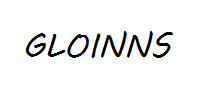Aki Machida
ドットコムバブル
2000年と言えばドットコムバブルでシリコンバレーは沸き返っていました。インフラが間に合わないので、保育所はどこも 100人待ち、空いているアパートは5件足らずで、見に行くと既に抑えられている状況でした。
90年代のアメリカはモノづくりで日本に負けてばかりでした。しかし、インターネットの普及で街には人が溢れ、家族が路頭に迷わないように、2ヶ月前に生活基盤確保の為だけにシリコンバレーに来て、とりあえず呼び寄せられるように準備しました。
今はインターネットがありますし、色々な方が赴任情報を纏めてくれていますから、当時の私達の苦労はご理解いただけ無いと思います。ちなみにTomorrowAccessの傍島さんが素晴らしいサイトを用意して頂いてますので、私のシリコンバレー奮戦記(生活編)にリンクがありますので、参考にしてください。
HP社は1999年に計測器と電子部品をアジレント・テクノロジーとして分社しました。計測器部門の強さと利益率が良く、分社と同時にNYSEに上場するという超優良企業で誕生したので、移動には全く不安はありませんでした。光学マウスセンサー担当のマーケティング課長としてUS本社で仕事に就きました。事業部長はかつての日本のマーケティング時代に日本駐在として来ていた上司ですから、居心地は最高です。
ただ、活動内容は殆どの生産顧客がアジアなので、朝はゆっくり出来るものの、毎晩真夜中までアジアの営業部隊との価格や納期(アロケーション)の交渉です。当時は世界最大のマウスメーカの開発本拠地はスイスでした。ですから着任後、ダンボールを開ける暇もなくヨーロッパ出張に行ってしまい、妻を泣かせてしまいました。
また、競合品の出現対応・対策と調整で忙しさは極度に達しました。言い出してここに来たのですから、弱音を吐くわけには行きません。大学卒業以来、一生懸命やることが私の第一ポリシーでしたから、徹底的に可能性を考え、実行し、幸いにも大成功を収めたわけです。この辺りの詳しい話は光学マウス成功物語に書き留めてあります。
着任一年目の記念日の朝、日本からの電話で起こされました。何かニューヨークで事故が起きたと。テレビをつけると貿易センタービルのひとつから煙が出ています。旅客機が突っ込んだらしいと。何故かはその時点では分からず、自己扱いでした。暫くテレビを見ていると、もう一機が近づいて、旋回して、隣の棟に突っ込み、激しい炎が飛び散りました。とても怖かったです。誰が攻撃したのか、これからどうなるのか、そんな不安の中、なんと2棟が全崩壊したのです。911テロ事件でした。そんな映画みたいな事ってあるのと思いました。多数の消防士や警察が巻き込まれたと思うと、胸が痛くなりました。
それから数ヶ月、景気の悪化でリストラが始まりました。日本もリストラが起きたので帰っても席がないよということになり、ならば移籍させて欲しいと申し出てグリーンカード申請をサポートしてもらうことになりました。役に立たない従業員なら、日本法人の人事付きなどという所属で帰されてしまうのでしょう。その時は既に貢献度があったので、粘り強さとクリエイティビティが認められたのだと思います。
10本の指紋採取の後、グリーンカード取得ができました。上司に、首にしていいか、と聞かれ、いや、それは困ると即答したら、冗談だよと、冷やかされました。つまりVISAで来ているお客様ではないという意味です。彼は「そういうことなんだよ」、と説明してくれました。ベルトを締め直す気分でした。
光学マウスの次はCMOSイメージセンサです。事業そのものはパソコンカメラで大成功を収めてました。しかし、次の成長分野を探す製品開発政策会議で携帯カメラに変更するよう提案。日本と韓国を回って、顧客ニーズを把握。現行のパッケージ型のセンサーでは顧客要求の正方形のエンベロープに収まらないため、チップオンボードのカメラモジュールを考え出し、韓国の新幹線内でアイデアを纏め、その晩ソウルからノートの図案をカシオのデジカメで撮ってR&Dにメールで送り、開発プロジェクトをスタートさせることが出来ました。
当初はマウス用のレンズを製造している会社にカメラ用レンズを作らせてしまい、妙な非球面でリングが現れたり、解像度も満足行くものではありませんでした。そこで、日本のJ-Phoneのベンダーに納めている府中のメーカを探し当て、その競合である栃木のメーカにもアプローチし、レンズを供給してくれる手配をしました。結果、最初のCIFサイズは北欧と日本の合弁会社の携帯電話に採用され、大ヒットとなりました。
次のVGAサイズのカメラモジュールは低背の要求から、主光線角の広いレンズを別メーから採用しました。屈折率が高いので、アッベ数が低く、色ズレが起きてしまいます。マイクロレンズの遠心上の非線形シフトも提案し、周辺光量比補正や色補正アルゴリズムを提案して、デモ機を作って性能を向上させました。
私の机の上には人形やマクベスのカラーチャート、NHKのテレビ分解能チャートを置き、各種の光源が使える、テストブースになっていました。NEDLという博物館で使用される東芝の蛍光灯もわざわざヨドバシで買って来る凝り様です。
しばらくして開発チームがGretagのライトボックスやPhotoResearchのモノクロロスペクトラムスコープを買ったほどです。こうした耳学問はベンダーさんや展示会で勉強しました。
日本のカメラケータイは殆ど買って特殊ツールでバラしました。回線契約しないと売ってくれないものの、高い途中解約費用を払えば、新機種に移行できましたので、次から次へ新機種を入手してカメラ周り、チップの位置とバイパスコンデサの数や動作ブロックまで調べまくりました。
VGAサイズのカメラモジュールはヨーロッパに続いてアメリカのケータイメーカにも採用され、何百億円という事業に成長しました。
メガピクセルに移行する頃になると、風向きが変わってきます。小さいサイズを維持するための半導体の線幅プロセスとの戦いや、低照度環境での撮影感度、更にはオートフォーカスといった要求が出てきます。
形状は依然として正方形です。あるモデルではカメラの歩留まりを考慮して、ソケットにしてほしいという依頼を受け、大田区のソケットメーカに低背の6ミリ角や8ミリ角のソケットを設計してもらいました。
元々CMOSイメージセンサーのビジネスモデルはDRAMのお古の装置を使うことでキャピタルアセットがタダ同然で作るから儲かる事業だったのに、DRAMと同じ先端技術が必要になって来て、他社の特許技術を使わないと低照度対応ができないということで、上層部が難色を示し始めました。
また、オートフォーカスはステップモータやコイル、ピエゾ、リキッドタイプ、LCD、EDOFなど種類豊富で、それぞれのサンプルを取り寄せ、駆動のアルゴリズムを開発チームと一緒に作り上げました。しかし、外部調達の部材が増えると利益率が下がります。5カ年計画では前のめりになると結論付けたところで、あっという間に事業売却の話に発展してしまいました。
折しも、半導体グループがアジレントから離脱して、投資会社の管理下に置かれることが発表されました。この時の、会社のモラルは最低でした。不安を感じた従業員はドンドン辞めてゆきます。昨日は誰、今日は誰といった具合です。
私はやることもないのに給料が出ますから、この時とばかり、社内のトレーニングに参加したり、書き貯めていたアイデアをじゃんじゃん特許申請しました。
余談ですがHP時代にこちらに出向したときも超多忙な時間を縫って、できる限りのトレーニングプログラムに参加しました。社内にはPCの使い方のアドバンスクラス、マーケティングの調査方法や、多変量解析、リーダートレーニングなど、マネージャに申請すれば簡単にサインアップさせてもらえます。HPやAppleがSVで第2の大学と言われる所以です。
そうこうしているうちに、CMOSセンサーグループはマイクロンに吸収されることになったのです。競合のマイクロンではどんなマーケティング展開をしているかとても興味があったので、遺留するオプションを捨てて、転籍するオプションを選びました。
今思えば我慢して遺留していれば、短期間に$20でIPOし、現在は何百ドルにもなってますから、きっと億万長者で悠々自適な生活を送っていたかも知れません。ただ、性格的に不満が少しでもあると変えたくなるので、やはりマイクロンに行って良かったのだと思います。
マイクロンに行って一番驚いたのは、事業推進していたマーケティングの副社長が日本人だったことです。向こうもびっくりしたようです。でもすぐに私がなぜSVで生き永らえているか理解してもらえました。
私の担当は当時のGSMのナンバーワン企業です。勤務時間は熾烈でした。
モジュールは八王子の光学機器メーカが作り、オートフォーカスは世田谷区の会社、アジアの購買は目黒と北京にあり、技術統括はフィンランドですから、就労は一日16時間近くになります。会社でカップヌードルの昼と夜を済ませて家には寝に帰るだけ。出張は全部ビジネスクラスです。でも日本行きだけだったのに、韓国に寄って来てくれと言われ、ソウルに着くと、旅行会社からヘルシンキに行けという連絡が来て、ひどいときは帰りについでにシカゴに寄ってくれという、人使いの荒さでした。
一年も経たないうちに、イメージセンサー部門を分離して別会社にする話が出てきました。どうしてなのか理解不能で、またもモラルはひどく落ち込んでしまいます。映画のワンシーンのような従業員解雇も目のあたりにしてました。辞める人がいるとその仕事が回ってきます。
あっという間に労働時間は文字通り24-7で休みがなくなり、遂には夜中の2時に帰宅する途中、運転中に目がまわりはじめ、高速の出口でハンドル操作を誤り、がけ下に落ちてしまいました。幸い、前輪駆動のシビックはかろうじて底から這いあがり、私も怪我はなく、なんとか自宅に戻りました。この事故で後輪が傾いてしまい、それでも次の日にブルブル震えながら走る車で出社して仕事を終えました。血圧が上がって、鼻血もあり、このままでは過労死すると予感しました。これで不満が絶頂に達したのです。
そして50歳で、飛び出す決心をしたのでした。(スタートアップへと続く)